わたくし小学校の先生をしているベールと申します。
2歳になる娘と妻の3人暮らしです。
昨年から、子どもの保育園の登園が始まりました。妻の勤め先が遠方なので、私が送り迎えをどちらもしています。
そのため、否応なしに朝はぎりぎり出勤、退勤は5時半までというしばりプレイで仕事をすることになりました。
今までのような働き方では、絶対に家庭も仕事も回すことができません。そこで、様々な教育書を参考にして、仕事のやり方を考えました。
そこで参考にした教育書の一つが若松俊介さんの著書「教師のいらない学級のつくり方」です。
「教師のいらない学級」をつくることで、少し先生がいない時があっても自分たちで行動できるような自立した子供を育てることができる。自分も業務の負担を減らし、娘の急な発熱に対応できるようにというWIN-WINな学級づくりの方針だと考えたのです。
今回は今年1年「教師のいらない学級」を目指して、自分がやってよかったと思ったこと、改めて本書を読み返し、「ここはできていなかったなあ」と思った反省点を書きたいと思います。
- 「教師のいらない学級」に興味があるが、実際にどうなるかが怖い
- なるべく学級経営の無駄を減らしたい
- 自分も楽をしつつ、子供も成長させたい
そもそも「教師のいらない学級」とは?
まずは、「教師のいらない学級」とは何でしょうか?全く先生がいなくても、自分たちだけで何でもできる学級?
そんな夢みたいな学級はあるのでしょうか。
若松俊介さんは「教師のいらない学級」を
子どもたち自身が「先生がいなくても大丈夫」と感じられる学級
と定義しています。
つまり、実際に教師は学級に必要ではあるが、教師に頼りっきりにならならず、自分たちで行動できる学級のことです。
若松俊介さんは次のようなステップで「教師のいらない学級」をつくることができると述べています。
- あらゆることを「自分事」にする
- 自分で考える土台をつくる
- チャレンジする姿を支える
- 上手くいかないを乗り越える
- 試行錯誤の土台をつくる
- 乗り越える姿を支える
- 子どもたち自身で成長する
- 教師の役割をぐっと減らす
- 次の学年へとつなぐ
わたしは今年1年ふり返ってみて、3の「子どもたち自身で成長する」というステップまでは意識できませんでした。
本書は「教師のいらない学級」の学級づくりに向けて、ステップを踏まえて、丁寧に書かれているのですが、今回は自分が本書を参考にして、実践したこと・その結果を書きます。
具体的な内容が気になる方は、ぜひ本書をお読みください。
成功したこと:自分たちで考え行動できる子供たちになった
結論からいうと、本書を参考にした「教師のいらない学級」を目指した学級づくりはこれまでにないほど効果があり、成功かはともかく、やってよかったです。
では、どのようなことを実践して、どのような効果があったのでしょうか。
わたしが「教師のいらない学級」にするためにしたこと
わたしが「教師のいらない学級」づくりを目指して、常に意識していたことは、「まずは子供たちが自分で考えるクセをつける」というということです。
例えばこんなことがありました。
1学期の私のクラスでは、給食や帰りの準備の開始が遅く、スムーズに進まないことが課題でした。
そこで、子供たちへ「このままでいいのか」と問いかけました。
子供たちはいやもっと早くしたいといいます。
「では、どうしたら早くできる?」と再び問います。
子供たちはみんなで「あーでも、こーでもない」と考えました。
そして、「タイマーを使って、目標時間内に準備する」という結論を出しました。
一学期に決めたこのルールは3学期までしっかり適応され、今は学校の中でもかなり準備が早い学級になっています。
このように、何か課題があったときには、先生ではなく自分たちが問題を認識し、どうなりたいのか考える。そして、方法を考えていくというステップを様々な場面で行いました。
キーワードは、「自分はどうなりたいか」「自分はどうしたらいいと思うか」です。
教師が「答え」を与えるのではなく、自分たちで「問題」を意識し、「答え」を探していくということを繰り返すことによって、「教師のいらない学級」を目指しました。
自分たちで行動できる子供へ
娘の急な発熱などで、急に休みを頂くことも多いですが、とくにわたしがいない時に、大きな問題が起こったことはありません。
代わりに入ってもらった先生からは、「昨年度と雰囲気が全然違う。成長したね」と言って頂くこともありました。
体育の時に、先生がいなければ先に体育の係が指示を出して、縄跳びの練習をしていたり、朝の会の歌も私がいないと音楽を流せないので、自分たちで考えてアカペラで歌ったりしていました。
少々教師がいなくても、自分たちで何とかできるという自信はあると思いますし、わたし自身もある程度、「この子たちならある程度自分たちでできるだろう」という安心感も生まれました。
失敗したと感じたこと3選
一方で、失敗したと感じたこともあります。本書に不備があったり、「教師のいらない学級」というコンセプトに問題があったわけではありません。
わたし自身の技術やマインド面でいたらなかった点がありました。これについて3点見て頂けたらと思います。
失敗①:子供に応じて、対応を変えていなかった
例えば、わたしのクラスに何回やっても、忘れ物を繰り返してしまう子がいます。
わたしは、その子に対して「忘れ物をしてしまうことについてはどう思う?」「何をしたら忘れないようになるかな?」と問いかけ続けました。
しかし、1年経った現状、その子の忘れ物グセは大きくは変わっていません。
子供によっては、家庭環境・子供自身の能力といった理由から、どうしてもできないこともあります。
本書にも「うまくいかない」ことについて一緒に考えるという項目がありました。
子供によっては、もっと教師が具体案を出してあげたり、困り感に寄りそいながら支援してあげる必要があったのかもしれないと感じています。
失敗②:都合のよいように子供たちを動かそうとすることがあった
学校の中では、どうしても教師や学校の思いがあったり、活動に時間をかけることができず、子供たちの思いと違うことをすることもあります。
わたしはなるべく子供たちが自分で考えて、活動してほしいという意識がありました。そこで、誘導するような感じで、子供たちに問いかけてしまうことがありました。
たとえば、「〇〇になりたいよね?」とか、「〇〇した方がいいと思うんだけど、どうかな?」というような言い方です。
当然、子供たちの考えや思いと違うことをすることはあります。そんなときは、「悪いけど、こっちで決めさせてくれ」と前置きをした上で、教師の主導で進めることがあってもいいのではと思いました。
無理に、子供たちが主体で考えるというところにとらわれると、逆にイヤらしい感じになってしまうような気がしましたし、子供たちもそれを感じ取ってしまうからです。
失敗③:子供に寄り添い切れていなかった
私としてはこの失敗が一番大きな失敗です。
3学期に子供同士の暴力行為が発覚しました。実はこの件は1年間断続的にあったことが分かったのです。
どうも先生や人が少ないときにあったようで、アンケートなどもありますが、それにも書かれていないので私も把握できていませんでした。
「なぜ途中で言ってくれなかったのだろう」と思いました。
自分の学級経営を振り返って、思ったのは「わたしは、相談しやすい先生だったのかな?」ということです。
子供たちが自分の力でできることをするという「教師のいらない学級」はとても素晴らしいです。
しかし、教師が必要な時に機能しない学級になってしまうとこのようなことになってしまうのではないかと考えました。
自分たちで考えるクセをつけることはとても大事ですが、自分たちでどうしようもない問題を教師に伝えて解決することも必要な力です。
「必要な時には、先生に頼ってくれ」というメッセージをもっと伝える必要があったのかもしれないと感じました。
本書にも、「教師自身が振り返ること」の大事さが説かれています。
手のかからなくなった子供たちに安心してしまっていた点もあります。しっかりと子供たちを客観的に見定め、現在地をつかむ必要があるのです。
最後に
仕事や家庭でやることが盛りだくさんの先生にとっては、この「教師のいらない学級」という方向性はとても良いものだと思います。
しかし、『自分が楽をすること』を意識すると、本来の目的である『子どもの成長』を見失ってしまう危険があります。
楽になった分、「子供にしっかり寄り添おう」、「一人一人を見つめよう」という意識が大事なのです。
結局それが、子供たちの安心にもつながり、その後の対応を楽にすることにつながります。
来年度は今回の反省を踏まえて、「教師のいらない学級」をつくっていきたいと思いました。
ここまで読んでくださってありがとうございました!
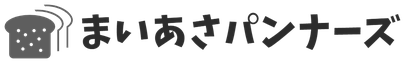
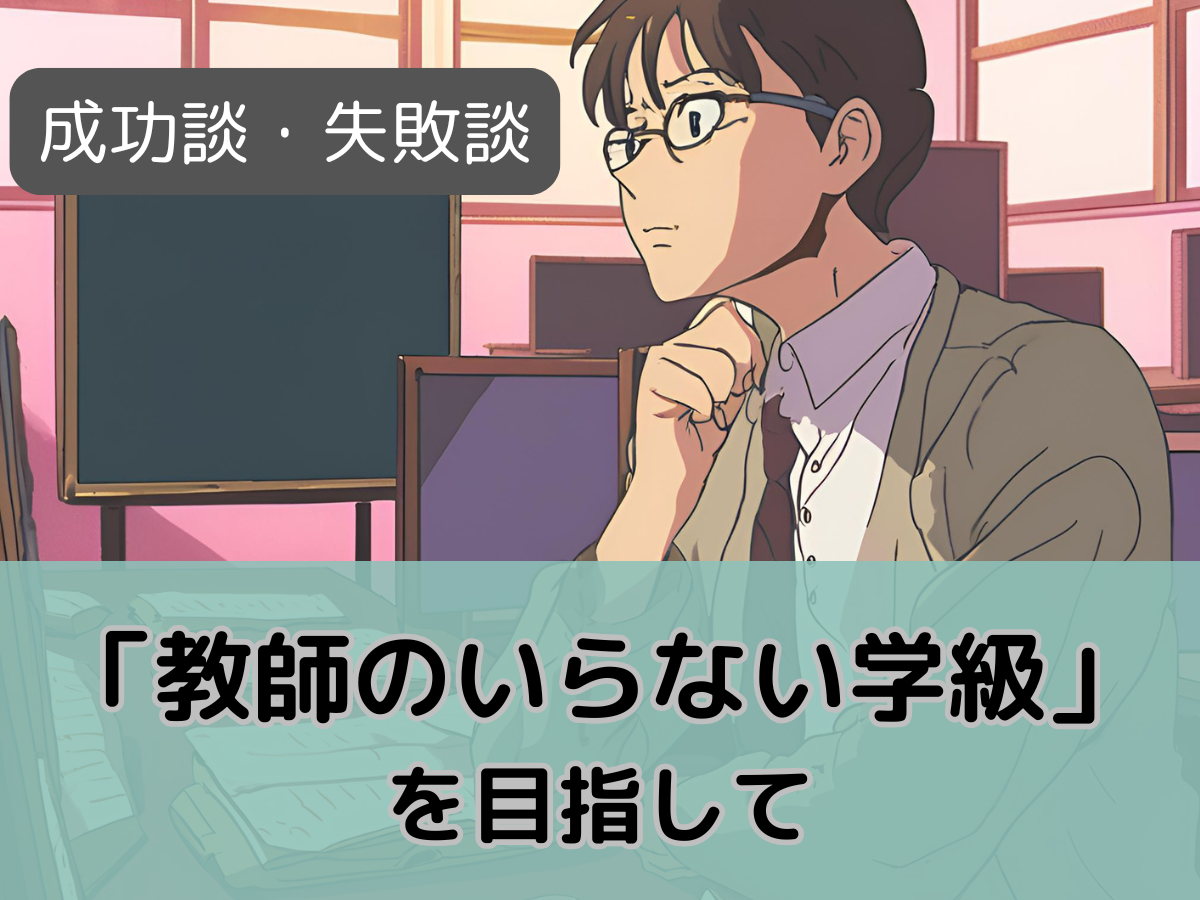
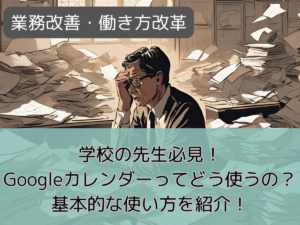
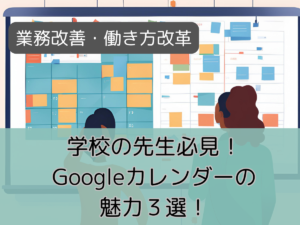
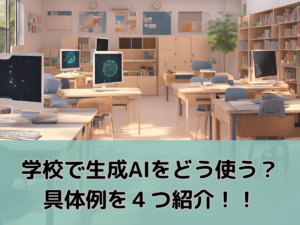
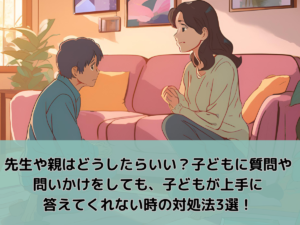
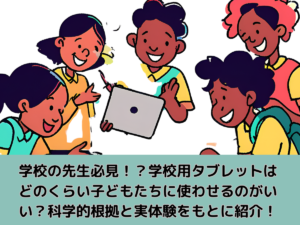



コメント