2019年文部科学省からGIGAスクール構想が発表されて、ほとんどの学校現場にタブレット端末が導入されました。
授業の幅は広がるし、教員同士の連絡などもしやすくなって業務改善につながった面もたくさんあります。
一方で学校現場の中や、他の学校の先生とも話をする中で星の数ほどの問題点もあります。
その中でも、特に頭を悩ませているのは、どのくらい子どもに自由にタブレットを使わせるかということだと思います。
今回記事はでは、学校でタブレットをどのくらい子どもに使わせるのか、またルールを、科学的根拠と実体験をもとに解説します。
今回の記事は次のような人におすすめです!
- タブレットとの付き合いかたが分からない先生
- 上手く使いたいけど不安な先生
- どのようにルール作りをしたらいいのか分からないICT担当の先生
学校現場の実態と結論

わたしは小学校でICT担当をしています。なので、様々なタブレット端末の問題が上がってきます。具体的には、
- 勝手に設定を変えて、動かなくなった
- アプリを勝手に入れて遊んでいる児童がいる
- ブラウザ検索は自由にできないはずなのに、フィルターをかいくぐって調べている
- キャラクターの写真を調べて、写真フォルダに大量に貯めている
など、あげればきりがありません。
では、タブレットの導入を規制する方向に向かうべきなのでしょうか?
わたしはそれも時代と逆行していると感じます。これからの社会はこうしたメディアと上手く付き合っていく必要があり、その機会を奪うことはあってはならないと考えるのです。
子どもが使えば使うほど問題は起こります。そのつど、指導しながら上手に活用できるようになればいい考えています。
しかし、一日中ずっと使い続けるのは問題です。
わたしの結論は「目的とルールを明確にした上で、ある程度自由に使わせよう。ただし制限は絶対に必要」というものです。
「どうして制限する必要があるのか」への科学的な理由

どうして制限する必要があるのでしょうか?
幼児にスマホやテレビを見せすぎることへの悪影響については様々なメディアで語られますが、小学生以降の子どもについて論じたものはそこまで多くありません。
さらにGIGAスクール構想のもあり、児童にICT機器を使わせることを推奨する流れもあります。
ではなぜ、制限を必要だと考えるのか。
タブレット端末の使用を制限することへの理由は色々ありますが、今回は子どもの能力面への影響に焦点を当てて紹介します。
カナダのオタワ大学の研究では、スクリーンタイム(スマホやテレビを見る時間のこと)が10歳前後の子供の能力にどのように影響を与えるか調査をしました。
カナダの児童・青少年向け 24 時間運動ガイドラインでは、8~11 歳の児童に対して、1 日あたり少なくとも 60 分の身体活動、1 日あたり 2 時間以内の娯楽用スクリーン時間、および 1 晩あたり 9~11 時間の睡眠を推奨しています。
スクリーンタイム(スマホやテレビを見る時間のこと)は1日2時間以内が望ましいとした上で、以下のように結論付けました
10代前半や10代の若者のスクリーンタイムが長いことには懸念すべき理由があります。(中略)スクリーンタイムの推奨値を超えた8~11歳児は認知評価のスコアが低く、推奨値の順守が認知スコアの全体的な変動の約5分の1を占めています。スクリーンタイムと睡眠不足の組み合わせも、同じ年齢層における衝動性の高まりと関連付けられています
要するに、スクリーンタイムが長いと
- 認知能力の低下につながる可能性がある
- 衝動性が高まる可能性がある
ということです。認知能力とは、言語力・計算力・記憶力などの日常生活を送るうえで欠かせない能力のことであり、衝動性が高いと感情や行動のコントロールが難しくなります。
スクリーンタイムだけではなく、
アメリカ小児学会APPも、6歳以上の子供に対しては、メディア使用の一貫した制限を設け、他の健康的な活動を妨げないようにすることを推奨しています。スクリーンメディアの使用時間をきちんと決め、睡眠、身体運動、その他の健康行動の時間を取ることが望ましいということです。
どのくらい子どもに自由にタブレットを使わせたらいいのか

では、どのくらい自由にタブレットを使わせたらいいのでしょうか
教育現場にいる経験を踏まえて、自分の考えを書きます。
一日ずっとタブレットを使わせるのはやめよう
わたしは小学校3年生の担任しています。
授業中以外で自由にタブレットを使えるのは
- 給食を早く食べ終わったとき
- 雨の日の休み時間
- 係活動などで担任が必要だと認めた時
としています。
一日の中で授業中にタブレットを使うことも多くありますし、家に帰ってもスマホやテレビに触れないという子は少ないです。
上に書いたように、能力面の低下も考えられますし、目が疲れるなど健康面での影響もあります。
子どもが体を動かしたり、コミュニケーションを取ったりする機会も増やさないといけません。
なので、子どもと話し合いながら、時にはこちらからルールを決めることが大切だと考えるのです。
自由にタブレットを使える時間をこのように決めたのは、次のような理由があります。
給食を早く食べ終わったとき
給食を早く食べ終わったときを認めているのは、給食の残り時間だとスクリーンタイムが大したことはなく、時間になったら全員で合掌するので、止めないといけない区切りが明確だからです。
子どもが「まだやりたい」と思っても、そこで踏ん切りをつけてさっとやめるのも、子どもの力を鍛えることにつながると思います。
雨の日の休み時間
雨の日は、外で遊ぶことができないのでテンションが下がったり、どうしても室内で騒いだたりしてしまう児童がいます。雨の日だけとしておけば、毎日タブレット漬けになることもありません。
雨の日も楽しみになったり、室内でも静かに過ごしやすくなります。
係活動などで担任が必要だと認めた時
クイズ係で調べたいなど係活動で使いたいときもある程度認めています。ただし、先生の許可なく勝手に調べることは認めていません。ここをおろそかにしてしまうと、ルールがなあなあになってしまったり、曲解して先生の想定外のことをしてしまったりします。
子どもがタブレットをどのように活用すると良いのか、考えるいい機会にもなると考えています。
これについては正解はないと思うので、学級でみんなが納得できるルール作りをすると良いです。
「学習のため」という目的を何度も伝え、子どもに考える力を身に付けさせる
子どもたちにはタブレットは鉛筆やコンパスと同じで「文房具」だと伝えています。
あくまで学習のために使うものであり、それに即さない使いかたは自由に使える時間であっても認めません。
でも、「学習のため」ってすごくふわふわしていますよね。私としてはそれが良いと思うのです。
A君がタブレットを使って遊んでいるように見えたとします。すぐに駄目です!と注意するのではなく
先生:それって学習にどう関係があるの?
と聞きます。
もしもA君が答えられなかったら、注意しますが
A君:社会の時間で世界の国について勉強したよね?グーグルマップで他にどんな国があるのか調べたくなったんだ。
など、こちらが「なるほどな」と思う返答をしたときには、クラスのみんなに聞いてから認めることもあります。
「学習のため」という抽象的な言葉を使うことによって、子どもたちの行動の「余白」をもたせ、考える余地を作ることが大事だと思うのです。
ルール違反には毅然とした態度で!
ある程度自由を認めると、時間を守れなかったり、自分勝手な使い方をする児童は必ず出てきます。
わたしのクラスでも1学期は何度も指導しましたが、「どのように学習に関係があるのか」問い続けるうちに、現段階の1月では、明らかに遊びで自分勝手にタブレットを使用する児童はほとんどいなくなりました。それだけではなく、「こういう目的で、このように使いたい」と考えて担任に伝えてくる児童もいます。
子どもは好奇心がおうせいなので、ついつい色々なことをやってしまいます。やはりそれに対して歯止めをかける役割がいりますし、それは先生がやるべきだと思います。
さいごに
タブレットの使わせ方については、わたし自身も試行錯誤している状態です。
タブレットの導入が先生を苦しめたり、子どもの能力を低下させたりするものではなく、上手く機能するベストの方法を見つけていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
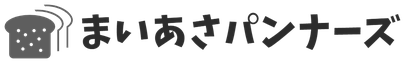
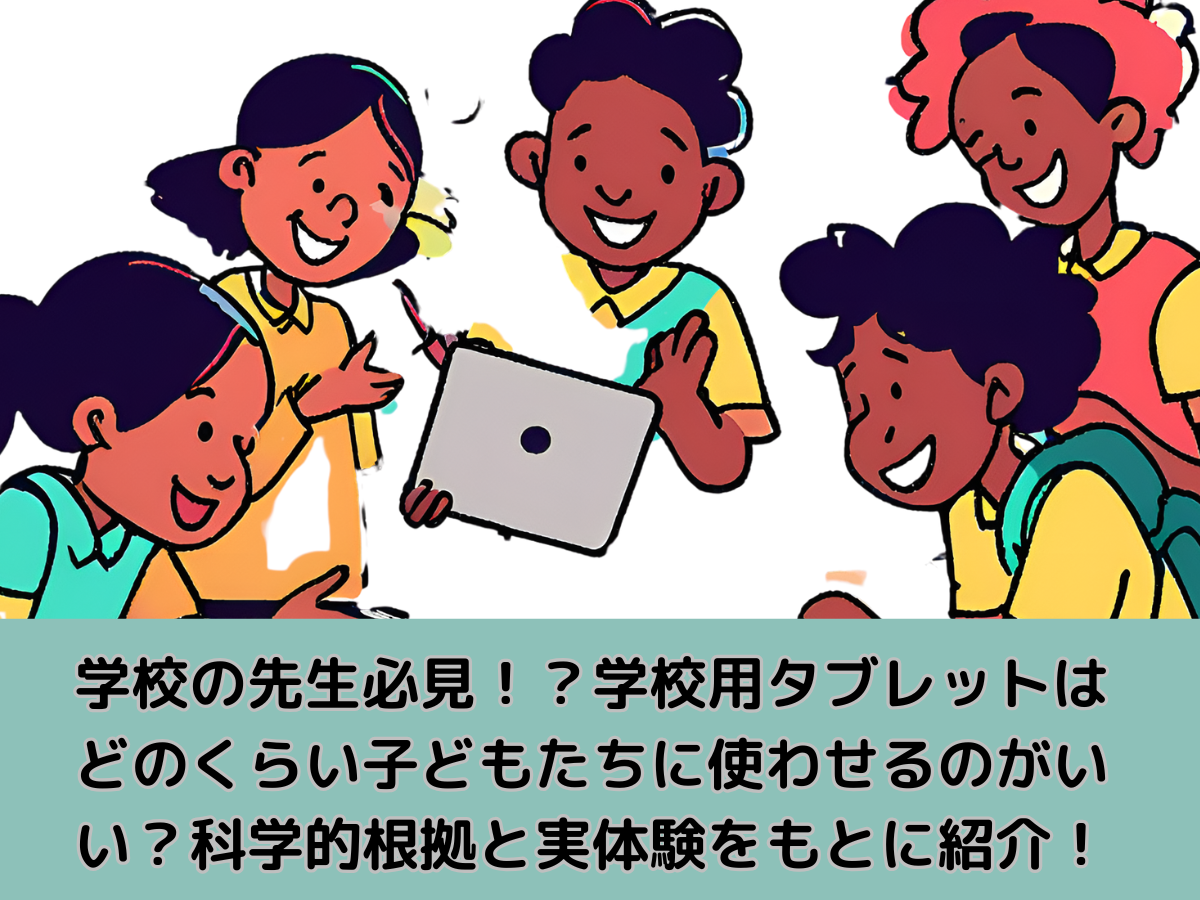
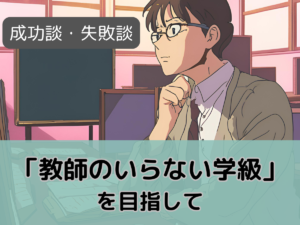
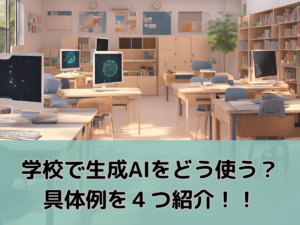
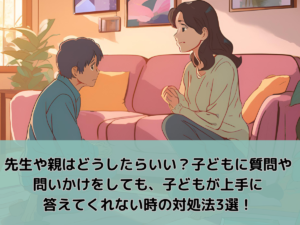





コメント